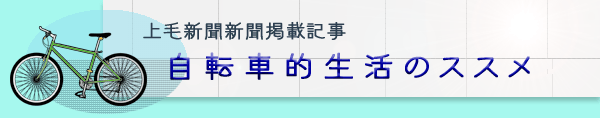|
| 自転車のシートポストに付けた点滅型のライトと反射板 |
目の前は青信号。交差点の横断歩道を渡っていたのに、居眠りの軽自動車にはねられてしまうなんて―。先月19日、前橋市南町で自転車3台が車にはねられ、1人が死亡、2人が重傷を負う交通事故が起きた。
重大事故には至らなくても、自転車に乗っていて、ヒヤリとする体験は結構多い。車に幅寄せされたり、信号で右折する車と接触しそうになったり―。深夜には、“ヒヤリ確率”はもっと高まる。
私の帰宅時間は深夜零時前後。ロードレーサーを買ったばかりのころ、県道前橋長瀞線バイパスを快調に走っていた時、後ろから追い越す車に「死にたいのか」と怒鳴られたことがあった。
多くのドライバーは、「自転車は歩道を走るもの」と思っている。最近は歩道が色分けされ、歩道上に自転車マークがきっちり描かれている。だが、道路交通法にのっとれば「自転車は車道を走る」のが基本なのだ。外国では、当たり前のルールが日本では「変容」したままだ。
交通戦争が叫ばれた1970年代、車道での自動車と自転車の事故が急増、78年に道路交通法が改正され、自転車は「歩道も走行可」となった。また、日本では、歩道を走るのに適したママチャリ(軽快車)が自転車の主流であるのも、一因かもしれない。
私を怒鳴ったドライバー氏も、自転車が車道を走っていたのが、許せなかったのだろう。一応、私は反射材を足に付け、前照灯をつけて走っていたのだが、ドライバー氏には薄暗くて、よく見えなかったのかもしれない。
事故を完全に避けることはできないが、自転車に乗る側が、ちょっとした工夫で安全性を高めることもできる。「怒鳴られ事件」以来、私は夜間、点滅ライトを装着するようにした。ヘルメットは蛍光色で、目立つのものを選んだ。「ここに自転車が走ってます」と主張することが、まず大切だと思ったからだ。
|