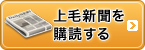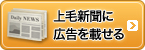世界遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群
製糸場工女の役割、境遇解明 富岡市が研究組織
更新日時:2017年8月18日(金) AM 11:00
世界遺産、富岡製糸場について群馬県富岡市は操業中、女性労働者が果たした役割を解明する取り組みを加速させる。有識者による研究組織を立ち上げ、115年にわたる操業期間を多面的に調査。学術的にまとめて国連教育科学文化機関(ユネスコ)に報告する。
研究組織の発足は、製糸場が2014年に他の3資産とともに世界遺産登録された際、ユネスコから女性による技術伝達の役割や労働環境、社会的境遇について研究を深めるよう勧告されたことを受けた対応。「女性労働環境等研究委員会」とし、市の委嘱を受けた有識者の委員7人が2年かけて研究する。
1872年の操業開始から1987年の操業停止までの女性労働者の仕事ぶりや福利厚生制度、製糸技術の普及などについて、各委員が分野ごとに研究する予定。半年に1回程度会合を開き、中間報告する。
製糸場の労働環境解明に向け、市は昨年度以降、片倉工業時代の元従業員を中心にしたネットワークづくりを進める。登録している元従業員約50人は必要に応じて委員の調査に協力する。
東京大大学院の鈴木淳教授(日本近代史)や富岡製糸場総合研究センターの今井幹夫所長(富岡製糸場史)、法政大の榎一江教授(経済史)らが委員となり、23日に市内で初会合を開く。今井所長は「工女がどういう技術を製糸場から持ち帰り、広めたかや製糸場を模した器械製糸がどう全国へ広がったか、研究していきたい」と話した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。
研究組織の発足は、製糸場が2014年に他の3資産とともに世界遺産登録された際、ユネスコから女性による技術伝達の役割や労働環境、社会的境遇について研究を深めるよう勧告されたことを受けた対応。「女性労働環境等研究委員会」とし、市の委嘱を受けた有識者の委員7人が2年かけて研究する。
1872年の操業開始から1987年の操業停止までの女性労働者の仕事ぶりや福利厚生制度、製糸技術の普及などについて、各委員が分野ごとに研究する予定。半年に1回程度会合を開き、中間報告する。
製糸場の労働環境解明に向け、市は昨年度以降、片倉工業時代の元従業員を中心にしたネットワークづくりを進める。登録している元従業員約50人は必要に応じて委員の調査に協力する。
東京大大学院の鈴木淳教授(日本近代史)や富岡製糸場総合研究センターの今井幹夫所長(富岡製糸場史)、法政大の榎一江教授(経済史)らが委員となり、23日に市内で初会合を開く。今井所長は「工女がどういう技術を製糸場から持ち帰り、広めたかや製糸場を模した器械製糸がどう全国へ広がったか、研究していきたい」と話した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。