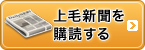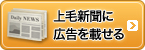世界遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群
「GM蚕」農家で飼育 国が承認 蛍光シルク量産化
更新日時:2017年9月26日(火) AM 11:00
遺伝子を組み換えて高機能シルクをつくる「GM蚕」の実用化に向け共同研究を進めてきた群馬県蚕糸技術センター(前橋市)と農業・食品産業技術総合研究機構(茨城県つくば市)は25日、緑色蛍光シルクを生産するGM蚕の一般養蚕農家での飼育を始めると発表した。遺伝子組み換え生物の飼育を規制するカルタヘナ法に基づき、22日に農林水産省と環境省が通常の養蚕に近い形での飼育を承認した。緑色蛍光シルクの量産化は世界的に例がなく、センターなどは付加価値の高い繭の生産普及、商品開発に力を入れる。
センターによると、同法の「第1種使用」で、農家での動物種の飼育が認められるのは国内で初めて。飼育は前橋市内の養蚕農家1軒が10月5日から開始。センターで卵から孵化 させたGM蚕12万匹を人工飼料で3齢まで飼育し、農家では3齢後半から桑で育てる。繭の生産量は160キロとなる見込み。
飼育に際し、天然種のガのクワコとの交配を防ぐため、蚕室の窓や入り口に網を張ったり、食べかすの桑の枝を破砕して処分するなどの措置が必要となる。
生産した繭は長野県岡谷市の製糸会社で生糸にする。京都市内の織物会社が販売主体となり、インテリア素材の商品化を検討しているという。繭の需要に応じて他の養蚕農家なども生産できるよう、センターが研修する。
昨年度、県内の養蚕農家に支払われた繭代は県などの補助を合わせて1キロ当たり平均3650円だった。県によると、高機能シルクを作るGM蚕の繭の場合、補助金がなくてもこれを上回る見込みで養蚕農家の収益性の向上が期待される。既存の蚕室を使えるため、最低限の設備投資で済む。
センターと機構は2年前から共同でGM蚕の飼育実験を実施。科学的なデータを基に昨年11月、農水省と環境省に養蚕農家での飼育を申請していた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。
センターによると、同法の「第1種使用」で、農家での動物種の飼育が認められるのは国内で初めて。飼育は前橋市内の養蚕農家1軒が10月5日から開始。センターで卵から
飼育に際し、天然種のガのクワコとの交配を防ぐため、蚕室の窓や入り口に網を張ったり、食べかすの桑の枝を破砕して処分するなどの措置が必要となる。
生産した繭は長野県岡谷市の製糸会社で生糸にする。京都市内の織物会社が販売主体となり、インテリア素材の商品化を検討しているという。繭の需要に応じて他の養蚕農家なども生産できるよう、センターが研修する。
昨年度、県内の養蚕農家に支払われた繭代は県などの補助を合わせて1キロ当たり平均3650円だった。県によると、高機能シルクを作るGM蚕の繭の場合、補助金がなくてもこれを上回る見込みで養蚕農家の収益性の向上が期待される。既存の蚕室を使えるため、最低限の設備投資で済む。
センターと機構は2年前から共同でGM蚕の飼育実験を実施。科学的なデータを基に昨年11月、農水省と環境省に養蚕農家での飼育を申請していた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

遺伝子組み換え蚕が生産した緑色蛍光シルクの繭