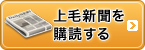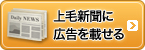世界遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群
明治後期の高山社をカラーで 養蚕学習の彩色写真 50枚見つかる
更新日時:2020年8月22日(土) AM 06:00
明治後期ごろの高山社蚕業学校の様子などを写したガラス乾板の写真50枚が、群馬県立歴史博物館(高崎市)に残されていたことが同館学芸員らの調査で分かった。彩色処理が施されており、生徒が養蚕を学ぶ情景がカラーで確認できる。調査を通じて、海外の最新機を輸入して蚕病消毒器の研究、開発に当たっていたことも新たに判明した。写真は細部まで鮮明で、創始者の高山長五郎の没後、体系化が進んだ高山社の状況を示す視覚資料として今後広く注目されそうだ。
高山家の子孫が寄贈した資料約1万4千点に含まれており、同館の佐藤有学芸員と藤岡市教委文化財保護課の軽部達也課長が昨年から今年にかけて調査した。サイズは8.2センチ角で、授業などで投影するスライドに使用するためガラス乾板に写し込んだとみられる。
見つかった写真のうち34枚は、高山社の2代目社長の町田菊次郎が記した「養蚕法」(1904年)と「最近養蚕法」(15年)に使用されていたため存在が知られていたが、白黒で解像度も低かった。今回の写真は元データに近い解像度とみられ、「養蚕法」の記述などと照らし合わせて情報を精査すると、蚕の餌の与え方、温度や湿度の管理方法などが詳細に分かった。
軽部課長は「成育段階に合わせて桑の刻み方を変えているなど、写真によって明らかになったことも多い。高山社跡を紹介する展示に生かしたい」と話す。
今回初めて確認された写真もあり、1900年前後ごろから輸入が始まった海外の蚕病消毒器を、高山社が早くから扱っていたことが分かった。写真にはホルマリン水を薬剤として噴霧するタイプの消毒器のほか、石油を用いて加熱し、圧力を高めて薬剤を噴霧するタイプなどが写っており、海外の最新機を試していたことがうかがえる。
佐藤学芸員は「一般の養蚕農家には高山社が考案した簡易で安価な消毒器を推奨していた。海外製品の導入は研究的な側面が強かったのだろう」と指摘。「養蚕農家に合った実用的な手法を考え続けたことが、高山社が国内で圧倒的に受け入れられる土台となったと考えられる」としている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。
高山家の子孫が寄贈した資料約1万4千点に含まれており、同館の佐藤有学芸員と藤岡市教委文化財保護課の軽部達也課長が昨年から今年にかけて調査した。サイズは8.2センチ角で、授業などで投影するスライドに使用するためガラス乾板に写し込んだとみられる。
見つかった写真のうち34枚は、高山社の2代目社長の町田菊次郎が記した「養蚕法」(1904年)と「最近養蚕法」(15年)に使用されていたため存在が知られていたが、白黒で解像度も低かった。今回の写真は元データに近い解像度とみられ、「養蚕法」の記述などと照らし合わせて情報を精査すると、蚕の餌の与え方、温度や湿度の管理方法などが詳細に分かった。
軽部課長は「成育段階に合わせて桑の刻み方を変えているなど、写真によって明らかになったことも多い。高山社跡を紹介する展示に生かしたい」と話す。
今回初めて確認された写真もあり、1900年前後ごろから輸入が始まった海外の蚕病消毒器を、高山社が早くから扱っていたことが分かった。写真にはホルマリン水を薬剤として噴霧するタイプの消毒器のほか、石油を用いて加熱し、圧力を高めて薬剤を噴霧するタイプなどが写っており、海外の最新機を試していたことがうかがえる。
佐藤学芸員は「一般の養蚕農家には高山社が考案した簡易で安価な消毒器を推奨していた。海外製品の導入は研究的な側面が強かったのだろう」と指摘。「養蚕農家に合った実用的な手法を考え続けたことが、高山社が国内で圧倒的に受け入れられる土台となったと考えられる」としている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

明治後期の高山社蚕業学校で学ぶ生徒たち(県立歴史博物館提供)