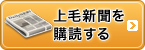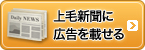世界遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群
暑さに強い蚕の新品種 群馬県が開発 夏場も収量と質 維持へ
更新日時:2019年1月17日(木) AM 06:00
近年の夏の猛暑による蚕の成育不良に対応するため、群馬県蚕糸技術センター(前橋市)は16日、暑さに強い新たな蚕品種を育成したと発表した。猛暑でも通常の品種に比べて高品質を維持し、1割以上多い繭の収量を見込める。昨夏の記録的猛暑で、本年度の県内の繭生産量は前年度比1割減の41.07トンに落ち込むなど、高温による障害が顕著に表れており、経営安定のため農家などから対策を求める声が上がっていた。今年夏に農家で実証飼育試験を行い、実用化されれば、9番目の県オリジナル品種となる。
同センターは2012年度から新品種の育成を始め、暑さに強い日本種原種「榛 」と中国種原種「明 」を交配した交雑種を生み出した。昨年夏の試験飼育は新品種と、普及している夏秋蚕用品種の「ぐんま200」「錦秋鐘和 」を同じ条件で育てて比較した。
6月26日に掃き立てを行い、7月20日に上蔟 。桑を与える4~5齢の12日間の蚕室の気温を調べたところ、夜間も含めて平均気温は30度前後で、日中は40度に達することもあった。
飼育の結果、蚕3万匹当たりの収繭量は新品種が48.42キロに対し、ぐんま200が43.55キロ、錦秋鐘和42.62キロと1割以上の差が生じた。品質の目安であり、繭糸のほぐれやすさを示す「解じょ率」は新品種が77%に対し、他の2品種は50%台。新品種は過酷な環境でも生存でき、健全なさなぎの割合も94.30%と高かった。
県蚕糸園芸課によると、本年度の蚕期ごとの繭生産量は春蚕16.10トン(前年度比10%減)、夏蚕5.66トン(同19%減)、初秋蚕2.16トン(同26%減)、晩秋蚕13.83トン(同6%減)、初冬蚕3.33トン(同1%増)と、夏の減少幅が大きい。暑さを考慮し、養蚕農家が夏の生産を控える動きもあったという。飼育量の多い春蚕の5月に気温の高い日が続き、成育不良が発生したことも響いた。
同課は「猛暑でも育てられれば、養蚕農家の経営の安定を図れる。これまでより、蚕室内の気温に神経質にならずに済むので、生産者の労力軽減につながる」としている。
農家での実証飼育試験は夏蚕(7月)か初秋蚕(8月)の時期に行う。その後、9月中旬のぐんまシルク認定委員会での県オリジナル品種の認定を目指す。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。
◎最も過酷な7、8月に実証飼育実験へ
同センターは2012年度から新品種の育成を始め、暑さに強い日本種原種「
6月26日に掃き立てを行い、7月20日に
飼育の結果、蚕3万匹当たりの収繭量は新品種が48.42キロに対し、ぐんま200が43.55キロ、錦秋鐘和42.62キロと1割以上の差が生じた。品質の目安であり、繭糸のほぐれやすさを示す「解じょ率」は新品種が77%に対し、他の2品種は50%台。新品種は過酷な環境でも生存でき、健全なさなぎの割合も94.30%と高かった。
県蚕糸園芸課によると、本年度の蚕期ごとの繭生産量は春蚕16.10トン(前年度比10%減)、夏蚕5.66トン(同19%減)、初秋蚕2.16トン(同26%減)、晩秋蚕13.83トン(同6%減)、初冬蚕3.33トン(同1%増)と、夏の減少幅が大きい。暑さを考慮し、養蚕農家が夏の生産を控える動きもあったという。飼育量の多い春蚕の5月に気温の高い日が続き、成育不良が発生したことも響いた。
同課は「猛暑でも育てられれば、養蚕農家の経営の安定を図れる。これまでより、蚕室内の気温に神経質にならずに済むので、生産者の労力軽減につながる」としている。
農家での実証飼育試験は夏蚕(7月)か初秋蚕(8月)の時期に行う。その後、9月中旬のぐんまシルク認定委員会での県オリジナル品種の認定を目指す。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

蚕期ごとの繭生産量