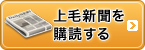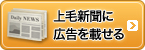世界遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群
荒船風穴の経営母体「春秋館」跡地 国史跡に追加 文化審答申
更新日時:2020年11月21日(土) AM 06:00
国の文化審議会(佐藤信会長)は20日、世界文化遺産でもある群馬県の荒船風穴(下仁田町南野牧)を管理した「春秋館」の事務所地1155平方メートルを国史跡「荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡」に追加することや、国史跡「浅間山 古墳」に外堀など周辺区域4658平方メートルを追加することなどを、萩生田光一文部科学相に答申した。春秋館の事務所は風穴と一体的に利用された重要施設で、日本の養蚕製糸業の発展を支えた役割が評価されている。
春秋館は、蚕種貯蔵能力「全国一」を誇った荒船風穴の経営母体で、1901~38年ごろに営業。事務所地は風穴の約7キロ東の下仁田町西野牧に位置し、主屋、土蔵、蚕室の3棟が現存する。風穴に貯蔵する蚕種は春秋館に届けられ、事務所が一時保管と仕分けの場所として利用された。春秋館は、蚕種の製造販売にとどまらず、改良や養蚕農家の指導なども率先して行った。
2010年に風穴が所在する4648平方メートルが国史跡に指定。17年に春秋館の土地と建物が町に寄贈され、調査を経て18年に町指定史跡になっていた。
浅間山古墳は高崎市倉賀野町に位置し、4世紀後半から5世紀初頭に造られた墳丘の全長約171メートルの前方後円墳で、同時期では東日本最大規模。1927年に3万2072平方メートルが指定されており、高崎市教委が2018年度の調査で確認した外堀と中堤の一部が追加対象となっている。
答申を受け、原秀男下仁田町長は「春秋館は、荒船風穴のかつての運営母体で、日本の絹生産の近代化を促した貴重な存在。地域に残された先人の偉業が重層的に認められた」、富岡賢治高崎市長は「古墳の範囲が広がり、追加指定となることは喜ばしい」とそれぞれコメントした。
このほか、世界文化遺産の田島弥平旧宅(伊勢崎市境島村)の周辺にある蚕種製造民家3軒を登録有形文化財(建造物)にするよう答申している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。
春秋館は、蚕種貯蔵能力「全国一」を誇った荒船風穴の経営母体で、1901~38年ごろに営業。事務所地は風穴の約7キロ東の下仁田町西野牧に位置し、主屋、土蔵、蚕室の3棟が現存する。風穴に貯蔵する蚕種は春秋館に届けられ、事務所が一時保管と仕分けの場所として利用された。春秋館は、蚕種の製造販売にとどまらず、改良や養蚕農家の指導なども率先して行った。
2010年に風穴が所在する4648平方メートルが国史跡に指定。17年に春秋館の土地と建物が町に寄贈され、調査を経て18年に町指定史跡になっていた。
浅間山古墳は高崎市倉賀野町に位置し、4世紀後半から5世紀初頭に造られた墳丘の全長約171メートルの前方後円墳で、同時期では東日本最大規模。1927年に3万2072平方メートルが指定されており、高崎市教委が2018年度の調査で確認した外堀と中堤の一部が追加対象となっている。
答申を受け、原秀男下仁田町長は「春秋館は、荒船風穴のかつての運営母体で、日本の絹生産の近代化を促した貴重な存在。地域に残された先人の偉業が重層的に認められた」、富岡賢治高崎市長は「古墳の範囲が広がり、追加指定となることは喜ばしい」とそれぞれコメントした。
このほか、世界文化遺産の田島弥平旧宅(伊勢崎市境島村)の周辺にある蚕種製造民家3軒を登録有形文化財(建造物)にするよう答申している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

国史跡に追加されることになった春秋館の事務所地(下仁田町教委提供)

浅間山古墳の外堀や中堤の一部が確認された追加指定地(高崎市教委提供)